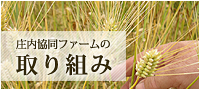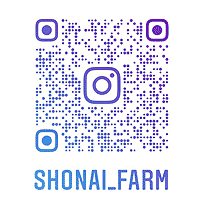2015年 柿圃場巡回
今年は、農産物全般が生育の早い年で、庄内柿も同様に早目の実りです。
例年の圃場巡回は10月20日前後に行っておりますが、今年は5日程早目の巡回です。
夏の好天も影響し玉伸びも良く、例年より一回り大きめの柿に実りました。 2015度庄内柿のご案内
アジア学院研修生受け入れ
2015年 枝豆目揃い会
収穫・出荷も本格的になりそうな時期をみながら、各生産者の収穫した枝豆を事務所に持参し目揃い会を行いました。今年は豊作基調ですが害虫被害のある生産者と比較的少ない生産者もおり、圃場や地域で違いがでている感じです。有機栽培である為、農薬対応も出来ず生産者泣かせです。
2015年 枝豆圃場巡回
写真左は7月23日に各生産者の圃場を巡回後に撮った生産者集合写真です。
今年は雨降りで巡回にも影響があり晴れ間を見ながらの撮影となりました。
写真右は今年の収穫・出荷に於ける確認事項の打合せです。各生産者の枝豆畑を巡回し、早生種の最初の収穫、出荷時期の確認を行いました。今年は、例年より収穫が数日早まりそうな感じとの事。又雨も少ない年で虫の天敵であるカエルも少ない為、害虫被害が心配との事です。出荷基準の確認では、黄化度合、虫食い、実入り、腐れ等に留意しお買い求めいただいた消費者の皆様から満足いただけるような選別をすることを確認しました。又有機栽培の為格付け書類等必要な資料・書類も多い為、再度記入方法の確認を行いました。
2015年5月27日 大麦部会 圃場巡回を行いました。
藤島中学生農作業体験学習
2015年5月20日・21日
藤島中学生農作業体験学習
地元藤島中学校より農業体験の受入依頼があり今年も引き受け致しました。
今年は3名で昨年より少ないですが、2日間の体験学習となりました。初日は弊社の概要説明、農作業体験、2日目は農作業体験中心の日程。農作業体験と云っても、環境整備、工場周辺の草むしりが中心で、かなりキツイ体験をさせてしまったのではないかと思っております。(よく頑張ってくれました)
以前は、製造作業も体験して貰いましたが、万が一の事故や衛生管理面から中止しました。
昨今は、地方と云っても子供のころから農作業させる農家も少なくなり実家での体験から地元企業への体験学習に変わってきたようです。
又、時代背景から、子供たちの顔写真やお名前は公開しておりません。
農事組合法人 庄内協同ファーム
体験学習受入 事務局
2015 スケジュール表.pdf
農業体験まとめシート:生徒1.pdf
農業体験まとめシート:生徒2.pdf
農業体験まとめシート:生徒3.pdf
藤島中学より.pdf
《庄内協同ファーム・生産者集会》を開催しました
第一部は、例年の通り活動報告・総括と次年度の活動計画を各部署より発表がありました。
(事業管理部、有機JAS委員会、生産履歴監査委員会)
生産・環境活動の総括・計画については、各部会を代表し米部会と干し柿部会からの発表がありました。特に干し柿部会からは、生産量の減少(生産者数の減少)に於ける今後の課題や対策等の報告がありました。ある意味日本の農業全体の課題の縮図の光景とも受け取れました。
第二部 研修・講演内容
1.報告 (やまゆり生活協同組合の現状とこれから)
やまゆり生活協同組合 常務理事 加藤 信吾氏やまゆり生協のあゆみや事業状況と ナチュラルフード講座①として塩をテーマに肉魚を使用しないレシピのお話がありました。レシピを工夫する事により、より栄養価の高い食べ物に生まれ変わる事が良くわかりました。(例えば 美味しい塩分の法則や炊飯に塩を活用する事など)
2.報告 (生活協同組合ナチュラルコープ・ヨコハマの現状とこれから)
生活協同組合ナチュラルコープ・ヨコハマ 常務理事 遠藤 匠氏
現状の事業報告(部門別の状況)や組合員拡大の取り組みと結果、今後の展開について又、全体的な課題と対策をわかりやすくまとめていただきました。
3.講演と実践 (家庭で出来る手当法) 自然療法実践者 井上 和氏
写真ではわかりづらいかもしれませんが、コンニャクを利用した、温熱療法をナチュラルコープの遠藤常務より体験していただきました。
大麦部会 圃場巡回を行いました。
《庄内協同ファーム・生産者集会》を開催しました
第一部は、前年度の活動報告・総括と次年度の活動計画を各部署より発表がありました。
(事業管理部、有機JAS委員会、生産履歴監査委員会)
生産・環境活動の総括・計画については、安心農産物生産委員会、部会を代表して、米部会と大麦部からの発表がありました。特に米部会からは過去7年前からの化学肥料及び化学農薬の削減状況や品種別、栽培区分の農法別(例えば、有機栽培のカモ除草、機械除草、紙マルチ、湛水管理)の面積の推移等。
第二部 研修・講演
1.講演 (福島の現状と私達が取り組んできた事)
講師 生活協同組合 あいコープふくしま 理事長 佐藤 孝之氏
佐藤理事長の資料より抜粋.pdf2.講演 (ブラシローラー型水田除草ロボットの現状)
講師 株式会社 テクノデザイン 今井 淳容氏3.講演 (水稲有機農業に関する試験研究成果報告)
講師 山形県農業総合研究センター 水田農業試験場
水稲部 主任専門研究員 安藤 正氏
《庄内協同ファーム・生産者集会》を開催しました
今年も第一部は、前年の活動報告、総括と次年度の計画を各部署より発表しました。特に有機JAS会議からは、有機管理規定の改定箇所の確認、安心農産物生産委員会からは、有機栽培農法の安定生産ポイントとして、アイガモ・紙マルチ・除草機・冬季湛水等各農法の優位点や弱点などの総括、又各作目部会からは、米部会より環境管理プログラム総括として2006年からの化学肥料・化学農薬の削減率(面積比)や除草方法(有機農法)の広がりなどの発表がありました。
第二部 研修・講演
Ⅰ 「らでぃっしゅぼーやのビジネスモデルと今後の取り組みについて」
講演: らでぃっしゅぼーや株式会社 代表取締役副社長 小関 純氏
130305radishboya.pdf へのリンクⅡ 「米の無肥料・無農薬で多収栽培は可能か」
講演: 山形大学名誉教授 粕淵 辰昭氏
130305kasubuti.pdf へのリンク★集会プログラム及び配布資料
130305seisannsyasyu.pdf へのリンク
昨年の役員改選期で若手生産者3名が新理事として就任しまし。今年の運営は、主管である安心農産物生産委員会の担当理事である、冨樫俊悦新理事を中心に運営を行いました。
庄内協同ファームだより NO141号参照
終了後の懇親会には、粕淵名誉教授・小関副社長も加わり講演の続きを各生産者と忌憚のない意見交換が延々と行われました。
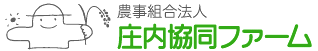























秋田テクノデザイン)-320x240.jpg)