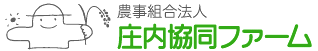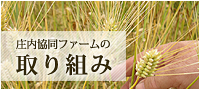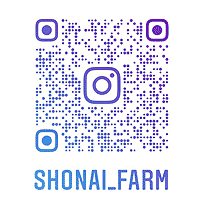枝豆部会が行われました
枝豆部会圃場巡回が行われました
枝豆の圃場巡回を行いました。今年も発芽率は問題なく、5月6月の播種・定植時は好天が続き順調に育ちました。7月から雨の日が多く、先日の大雨警報が発令された時は心配しましたが、今のところは大きな影響もなくほっとしています。
どの圃場も少し遅いペースながら生育しており、今も圃場に立つと枝豆の甘い香りがします。私たちの枝豆をお届けできることを楽しみにして大切に管理していきます。
枝豆の目揃え会を行いました
8月に入り、山形県内では甚大な豪雨災害がありました。被害にあわれました皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。
弊社は庄内地方で山形県の北西にあり、幸い大きな被害はありませんでした。ご心配くださいました皆様には感謝申し上げます。
各生産者より枝豆を持ち寄り目揃え会を行いました。
各生産者より良い品質で出荷してもらうために出荷基準を再確認し、持ち寄った枝豆を比べました。これから収量も増えてきます。皆様へ美味しい枝豆をお届けできますよう努力してまいります。
枝豆の圃場巡回を行いました
小雨の中、枝豆の圃場巡回を行いました。今年は発芽率もよく、播種・定植後も好天が続き、早すぎる梅雨明けも相まって順調に生育しました。7月中旬以降には雨の日が多く、幾分実の入り具合がスローペースになっていますが元気に育っていて、今も圃場に立つと枝豆の甘い香りがします。
皆様へお届けするまで大切に管理していきます。もう少しお待ちください。
2021.7.20 枝豆の圃場巡回が行われました
連日気温30度を超える日が続いています。当日も炎天下での巡回を行いました。
今春、定植時に晴れの日がなかなか続かずタイミングをみて苗を定植していました。その後は順調に生育し、巡回時には一つの枝にさやがたくさんついている圃場が多くありました。皆様へお届けするまであと少しお待ちください。
2020.7.20圃場巡回
今年は7月下旬の大雨で最上川中流域の市町村では家屋や農作物に大きな被害が発生しました。当庄内地区でも危険水域を突破し、公共施設に避難した方も大勢いましたが大きな氾濫被害はなく助かりました。
今年の天気は6月までは雨が降らず、乾燥により生育が進まず、7月からは一転雨が多く、土寄せ作業、除草作業が出来ないなど厳しい気象条件でした。それでも、枝豆はしっかりと育ち、皆様へお届けする事を嬉しく思っております。
2019年7月19日 枝豆部会 圃場巡回
2018年7月19日 枝豆部会 圃場巡回
今年は連日の晴天で巡回時は30℃を超えていました。全国的な猛暑の中では、ここ庄内地方はまだ恵まれているのかも知れませんが、それでもかなりの暑さで枝豆にとっても雨が欲しいところです。昨年は、初期の不安定な天候等が影響し生育遅れにより7月中の出荷は出来ませんでした。今年の生育は相応に順調で7月後半からの収穫・出荷が可能な状況です。これから1ヶ月半程の収穫が延々と続きます。
新たな若手後継者も加わり近年にない賑やかな圃場巡回となりました。

圃場巡回の様子
例年の通り各生産者の圃場を巡回し生育状況、害虫被害、収穫時期等の確認をしております。有機栽培で特に心配な害虫被害も少なく、今後適度な雨があれば生産者にとっても収穫量の期待できる年になりそうです。
目揃い会を行いました。
枝豆製品の袋を開けて、虫食いや、実入り、黄化具合等を確認しました。
各生産者の枝豆をみながら、今年の特徴(害虫被害、生育状況)などを情報共有しています。全体的には、昨年より害虫被害の少ない年のようです。
生産者が各自枝豆を茹でてきたものを食味しているところです。それぞれ若干の違いは
ありますが、今年も香り・コク・甘味のある枝豆に育ちました。食味は早生種になります。
2016年7月20日 枝豆部会 圃場巡回
今年の状況
例年よりやや不作基調か(昨年は大豊作でした)晴天が多く、雨の少ない年です。
今後恵みの雨があると良いのですが。このままだと半作になる生産者もいるかも知れません。害虫被害については、いまのところあまり気にならない程度の感じです。
毎年豊作とは限らず、ある意味自然界もうまく出来ているものです。