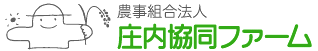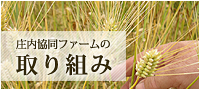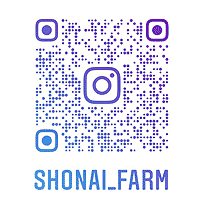庄内協同ファ-ムだより 1999年2月 発行 No.51
もうじき春、がんばるぞ!!
有機農業をめざして
今冬は、当地方には珍しく11月にビニールハウス、果樹、庭木が倒壊、倒木するほどの大雪があり、大きな被害をもたらしました。 また春から丹精込めて栽培してきた大豆を収穫目前に雪に倒されて収穫が出来なくなった組合員もいます。こんな調子で今年は雪の多い年になるのかと思ってそれなりに覚悟はしましたが、今日まで降っては消え、消えては降り、——-という事を繰り返してきました。
当地方は降雪量より吹雪がひどい事で有名なところで、今月13日朝の通勤時間帯に猛吹雪による視界不良で停車したライトバンに後ろから次々に追突、合計52台約300mにわたって玉突き衝突をし、軽いけがで済んだが事故車の撤去作業のため道路は7時間余りも全面通行止めになった。————- こんな大事件もありました。
このようないろんな事はありましたが、季節は確実に春に向かっていて、小鳥のさえずりは日増しに数を増し鳴き声にもつやと張りを増しつつあります。もうじき始まる農作業に向けての計画をいろいろとおぼろげではありますが、立てています。
今年は特に2001年から施行されるであろう有機農産物の認証制度に向けて、当組合でも今冬勉強会を何度か催し、出来るところから積極的に実践していく事になりました。
発ガン性の疑いがある農薬はもちろん、内分泌攪乱物質の疑いがあるものやダイオキシン発生の疑いのある農薬をリストアップし、それは出来る限り使わない、またどうしても使わざるを得ない物については代替の物を探し工面する。
また、栽培概要を作物別に作り、実際作業にあたったら何時どんな資材を使い、どんな作業をしたのかを記録、記帳する事を習慣づけてデータとして残し、それを基に更なる栽培的に向上を目指し、化学肥料、化学農薬に頼らない農業を行いたいと私は思っています。
畑作物では無農薬栽培を始めてかなりの歳月経ちましたが、化学肥料使用からは完全には脱却出来ずにいましたが、昨年から本格的に微生物の力を借りての“ぼかし肥”(醗酵肥料)作りを始め、今年はなんとか化学肥料からの脱却を考え、実行したいと思っています。
今年ももうじき春、お米はもちろん、大豆、野菜、など皆さんに安心して食べていただける農産物作りに励み、農産物といっしょに私たちの“元気の元”もいっしょにお届けしたいと思います。
スケッチ 1 村のうたから
♪ 土口名物、数々あれど
春はもうそう竹 夏はすもも 秋は伝九郎さわし柿よ 冬はふき山 銘産地 ♪
「や-っと来た-。吹雪で前は見えないし、もう少しでふき山さ、突っこむどこだっけ!」 悪天候の中、ひっしの思いで加工場に通勤して来る人達の声を聞き、ふと、このうたを思い出しました。そう、ここ土口はふき山名物だもの!
この冬、何回となくやって来た地吹雪の舞う、強い冬型の天気、日本海側から吹いてくる強い西風が南北に細長く並んだ村の家々にあたり、家の西側に通った道路は、風の通り道に添って雪が波のようにたまっていき、通れなくなってしまいます。
このうたは、40年前、青年団の中から生まれ、カラオケの無い時代、酒をのんでは歌われ、村対抗の運動会の応援歌としても、村の人達に親しまれてきたうたです。
夫達には子供の頃、遊び廻った風景と重なり、なつかしい味となっている土口すももも伝九郎柿も少なくなってしまいました。
土口すももは、実が小さめで、赤く、とても酢っぱいすももで、この地に合っていたのか、たくさん穫れてたそうですが、河川改修で畑が削られ、地下水が高くなったりで、我が家に一本、それも一枝しかなくなってしまいました。老木なのですが、毎年20個ほどの実をつけてくれます。
伝九郎柿は、お湯で渋抜きをする在来種の柿ですが、現在の庄内柿、平核無柿に枝継ぎされてしまいました。
40年の年月は、村の名物もうたの中だけに残されてしまいました。我が家の三人の子供達のなつかしい味は何でしょうか?
ふと考えてしまいました。
冬の間に食卓にのぼる塩蔵品。季節の山菜や野菜を一年かけて保存し、野菜の少ない冬の間に食べる昔からの知恵。
春のフキ、ワラビ、ウド、イタドリやミズ等の山菜、夏のナス、秋に漬け込んだたくあんや青菜漬けを塩抜きにしてはけんちん煮にして食卓に上げ、楽しんでいきたいものです。
スケッチ 2
今春、組合員(冨樫俊一・静子)の息子の「俊悦」さんが(23歳)、メンバ-の家族の中から初めて就農し後継者として、庄内の地で羽ばたく事になりました。
先日、その就農をささやかに祝う会を有志でおこないましたが、その時に、先輩として五十嵐良一が贈った言葉を、ご紹介します。
はなむけの言葉を、と言われたのですが、なかなか立派な事など言えないわけです。ですから、私の言葉でなく、私が大切にしている言葉を贈ります。
『稲の根に着目し、その事を原点とし、基軸として、米の単収増を実施し「諸作物の栽培を計り」経営に目をおよぼして「三川の農業、さらに」庄内の農業、そして社会を展望する。』
これは、昭和59年3月24日に、稲の根の研究者、川田信一郎氏(東大)が、三川で稲の根と題して講演した時のものです。
人間の器官の中で衰えないのは頭脳だ! 老人とは、少年に生きていく知恵を与えなければ…と。ソウゼツな講演でした。翌年か、翌々年に亡くなってしまいました。
どうか自分を大切にし、体も大切にし、家族も大切にし、自分の立場から大きく視野を広げ、農業にいそしんで下さい。
庄内協同ファ-ムだより 1999年1月 発行 No.50
自分の作ったコメは自分で食べたい、
売りたいという農家の特権を守るために。
例年にない雪の多い新年を迎えております。私達の農産物を食べて下さる皆様、今年もよろしくお願いします。
1月1日欧州単一「ユ-ロ」が誕生したが、ある新聞に欧州内の農産物自由化と為替変動を直接に影響をうけた農産物価格が1/2に下落した国もあり、直接所得保障制度はあるものの規模拡大した農家には負債だけが残り、経営計画もたたずに途方にくれているという記事が載っていた。
私達が目指してきたものは、ただ単にスケ-ルメリットを求めた規模拡大路線や生産された農産物の原料出荷だけではなく、労働コストが価格に正当に生かせる加工品として、又、安全性とおいしさと生産者のいろいろの思いを農産物にこめて、食べて下さる人に直接送り届ける「確かさ、正しさ」を再認識したしだいです。
一定の関税化率を定めたコメの全面自由化有機農産物の基準認証問題も裏をかえせば自由化の条件整備と言えますし、まさに農産物すべてが輸入自由化の嵐の中に入ってしまったようです。しかし、その中で別の流れを作るべくしぶとく農家として生き残ってゆく覚悟です。
今年、庄内協同ファ-ムとは別に集落の仲間と共同でミニライスセンタ-を作る予定です。自己所有の乾燥機、もみすり機が古くなったためと集落に隣接して、住宅団地が造成され新しい住民からの粉塵、騒音の苦情が予想されるからです。
農家同士なら、お互い様なのであまり問題にはなりませんが、いろいろな職業の人が増え、農家の人が少なくなったからです。
ふしぎなもので農業を離れてしまえば粉塵、騒音が気になってくるようで、直接苦情が出ないうちに、自主的に住宅地から離れた所に共同で新築することになりました。
先住民の思いやりとでも言いましょうか、人が良すぎると言いましょうか。
一般のライスセンタ-は、生産者のコメが混じってしまいますが、このミニライスセンタ-は、刈り取ってきた籾を個別に乾燥調整する自己完結型です。
生産者それぞれコメの栽培方法が異なるために、自分の作ったコメは自分で食べたい、売りたいという農家の特権を守るために個別に管理することにしました。生産者が特定されたコメは協同ファ-ムの精米センタ-で精米され供給されます。
建設目標は、設備を整えた割には乾燥調整利用料が日本一安価なライスセンタ-です。 これをきっかけとにして、他の農業機械の共同利用にも結びついてゆければ、更に欲張って地域の後継者にうまく引継いでいければと願っています。
今年はじっくりと「協と共」の意味を考える年にしたいと思います。
スケッチ”我が家のお正月”
この家の一員となって21回目の春、長男20歳の春を無事に迎えた。21年をかけて築き上げてきた家庭に自分たちの背をはるかに越えた長男、次男がいて生意気盛りの長女がいる。老いてますます元気な父がいて、働き者の母が健在である。
大晦日の夜ふかしがたたって、なかなか起きあがれない元旦の朝、眠気をふっきるように台所へと向かい、お雑煮の準備を始める。 昔は、男達が焼いてくれた元旦の餅も、近年は、その風習もうすれたまま焼き上がってしまうことが多い。
夫はいつもと変わらず豚舎に出て、取り敢えず餌だけ与えて家に戻る。年末に揃った子供達を無理矢理起こして、家人と同じように神仏を拝ませ食卓につく。
元旦の朝は、お雑煮の他にはとりたててご馳走はない。今流の重厚なお重に色どりよく並べられたおせちなど、我が家の伝統にはなく、キンピラごぼう、白たきと人参を真ダラの子で和えた子いり、それと、かまぼこ、漬け物がご馳走のすべて。御神酒が家長である夫からつがれ”新年の食”が始まる。
昔なら、年の数程食べたというお雑煮も夫が5個、私が2個、胃袋の目覚めない息子たちもようやく2個、娘は1個がやっと。
食事が済むと夫は、座敷の床の間に備えてあった我が家特製の大きなお供え(鏡餅)を神棚にあげ柏手を打つ。あらかじめ暦で調べておいた”歳徳の間”(その年一番良いとされる方向)に向いて正座している家族一人一人の頭の上に、お供えを乗せて齢を配って歩く。
健康に恵まれ無事に年を重ねられたことに感謝し明けた年の幸せを祈りつつ礼をすると朝の行事は終わる。
11時には村の公民館で年頭の酒宴が行われるので、夫はゆっくりとくつろいで、テレビを見る暇もなく、豚舎へと急ぐ。私は夫を送り出した後、ゆっくりと年賀状を見たり、書いたりしながら時をすごす。思い思いにこたつに足を入れて寝ころぶ子供達をながめながらすごせるのもお正月ならではのこと。そこにいるだけで嬉しい。
夕方、まだ戻らない夫を待たずに早めに豚舎に入り、作業をすませ、義弟を迎えに駅へ行く。半年ぶりの帰省に少し嬉しそうな、少し恥ずかしそうな顔をして穏やかに笑う幼馴じみの同級生を義姉が気取って迎える。
”東京は静かだった?”とか”去年のお正月もこんなに雪があったかな”なんて、たわいもないことを話題にしながら家へ戻る。
年に二度しか戻らない彼を迎えるとようやく我が家にもお正月らしく、精一杯のごちそうが並ぶようになる。家族全員が揃って、酒をくみ交わしながら嬉しいひと時をすごす。高三の次男までもが、お正月ばかりは許されて酒をついでもらう。
”この子が一番の酒豪になるのかな”飲みっぷりの良さに、思わずそんなことを想像してしまう私がいる。一年一年、大きくたくましく育っていく子供達をまぶしい思いで見つめている私がいる。
養豚と除雪作業はあるものの最小限の仕事をして、2日、3日とのんびりすごし、四日の朝。切符がとれなかったからといって早朝の”いなほ”で帰る弟を夫が送り、私は町の消防の出初め式の手伝いに出る。
町の婦人会に所属し支部長をつとめる責任上、特別な行事がある度に、駆り出される。あったかい麦茶を用意し、当地名物の玉こんにゃくをにて串にさす。
厳寒の中、わざわざで出向いてくれた来賓や観客をもてなすのが目的だ。こういう役目でもないと、めったに見る機会のない出初め式を見せてもらったが、十数年前、夫が分団長をしていた時には見られなかった、茶髪やロン毛をなびかせて、堂々と放水訓練をする若者を見て、時代の移り変わりを思った。
午後1時には、バスケ部の2泊3日の合宿に参加するという次男を送って、学校の寮まで約40分をかけて走る。187センチの長身を折りまげるようにして狭い車の中に乗っていた彼は、片手にむき出しのバスシュ-、背中に、ごちゃごちゃに丸めたユニホ-ムをつっこんだカバンを背負って、雪の中に駆けてゆく。
”又、来週!ケガをしないように頑張れ”かけた声を背中に受けて建物の中に消えてゆく。
5日の夕方、最後になった長男を、仙台行のバス乗場まで私が送る。年末年始の5日間、家庭教師のアルバイトを持ち帰ってきた長男は、馴れない雪道を、山伏の修行で有名な羽黒の山のふもとまで通った。
宿望が続く までは、行きも帰りも坂道で、運転の不馴れな長男を不安な思いで送り出していたが、慎重な性格が幸いして、ヒヤッとする瞬間もなく終わったのでホットした。雪道の運転も、雪国にとっては避けられない事、これも良い経験になったのかもしれない。
5日目のアルバイトを終えたその日に帰る、という長男をうらめしく思いながら車から降ろす。”母さん、仕送り少し減らしてもいいよ。”なんて言葉を残し、片手をあげてにっこり笑って帰る長男を車のバックミラ-で確かめながら車を出す。
1人減り、2人減り、3人目が帰って、淋しくなった広い家で、又、いつもと変わらぬ日常が繰り返される。この平凡な繰り返しこそが、幸せというものかもしれない。とボンヤリ考えながら、慌ただしく我が家の正月はすぎていった。そして、しばらくは、部活と勉強の両立に思い悩む娘の不機嫌をかわしながら、暮らしていくことになる。
今年も良い年でありますように
庄内協同ファ-ムだより 1998.12月発行 No.49
「農業という職業」から
先日、私が住む町の中学校で、”職業講話”と言うものをした。中学2年生に進路選択のために町内のいろいろな業種の人達に話を聞く機会を作るのが目的で毎年行われている。
町の中心産業である農業の話も是非という先生の申し出を断りきれず、出席したのはいいが、与えられた20分間、200人近い生徒の前で、何を話したか殆ど覚えていない。「 最近農業をしてみようと言う子供が居るのですよ」と言う先生の言葉を聞くにつけ、もう少し時間をかけて準備をすべきであったと反省することしきりである。
話を聞く子供達の顔を見ていてつくづく思うのが、自分の子供を含めてどれだけの子供達が農業に就くのだろうかということである。町内には1000戸近い農家がありながら、毎年新規に就農するのは居ても1人か2人というお寒い状況が続いている。
「農業は他人に縛られることなく、自分の生活が設計できる。」とか「自分の好きな作目を経営に取り入れることができる。」とか「これからの地球環境を考えると農業はリサイクル産業として、なくてはならない産業となる。」とか話しては見ても、3Kの言葉に代表される様に毎日地道に努力を続けた割には経済的も恵まれないと思われる仕事をいざ自分がやるとなると二の足を踏むことになるだろう。
私達は10年来産直を通じて、消費する人達の理解を深めながら、安全でおいしい農産物をつくる努力をしてきた。この間、遺伝子操作や環境ホルモンの問題など多くのことを学習し、生産の場でも今まで以上に、種子の確保から、化学肥料や農薬購入資材に頼らない食べ物作りの必要性を感じている。
しかしこの道は決して易しく平坦な道ではない。私も無農薬で柿作りに挑戦し、3年目で”収穫ゼロ”という悲惨な結果を経験した。私だけでなく庄内協同ファームのメンバーも、おそらく日本中の有機栽培や無農薬栽培に取り組んだ人達も大なり小なり同じ様な経験をしていると思う。経営的にも、周囲との関係を始めとする、精神的な面でもいろいろと苦労があるのだ。
これらの問題を克服しつつ、10年かかってようやく、集団で無農薬栽培に取り組むことにこぎ着けることができた今、新たに゙有機農産物の基準の認証”が始まろうとしている。
流通の方法(表示)を単純化し、消費する側がわかりやすくして欲しいという要求は解らなくはないが、農業生産はそれほど単純ではない、毎年変わる自然の天候に支配される部分が大きいのだ。安全でおいしい食べ物を要求する人はまず、この農業の宿命を理解しなければならないと思う。
すばらしい農業の技術を持って、有機栽培を実現した人、また理論的に実現可能だとする人は少なくはないと思う。しかし現実に国の基準に達する有機農産物は微々たる量で流通しても偉く高価なものになるということだ。安全でおいしい農産物を多くの人達が妥当な価格で食することができるためには、我々作る側と消費する側が今まで以上に理解を深め、後継者の育成を含め、時間をかけて基礎となる土壌を醸成しなければならない。一編の法律など役に立たないし、むしろ有害だと思う。
今回の有機の認証で、今まで、減農薬や減化学肥料を志し、産直に活路を見いだそうと地道に努力をしてきた農業者の多くが取り残されることになると思われる。負けてはいられないと思う反面、いったいどれだけの人達が、将来の日本の農業を背負い、本物の食べ物を作り続ける事ができるのか、そんな不安な思いが浮かんでは消える。
私の夢は「グリ-ン・ツ-リズム」
村々に羽黒山の山ぶしのほらがいが鳴り渡る頃になると、不景気に泣いたこの1年も幕をとじ始めます。
先日、印象に残った事はと尋ねられました。とっさには答えられない位、忙がしい1年でしたが、印象に残る程特に力を注いできたことは「グリ-ン・ツ-リズム」でした。
昨年と昨々年、私はヨ-ロッパに研修視察に行ってきました。そこで見てきたものが、ヨ-ロッパ型グリ-ン・ツ-リズムでした。 旅行好きな私は、どんな意味あいの旅行でもよかったのですが、たまたま農業関係の機関に属していたり庄内協同ファ-ムの女性達の長年の夢の実現ということで、二度もヨ-ロッパに行く機会に恵まれました。
その後、県が行なった勉強会に参加、私にも出来るのではと思うようになったのです。 イタリアで泊った農家ホテルは、馬小屋を
改築したステキな建物でした。我が家は、築100年の農家屋です。隣村の大きな地主から、婿に入った祖父が、実家のような造りの家として建てた家敷でした。厳格な祖父が柱や板戸を傷つけるのを禁じ大切に住んでいた家でした。
道楽人だった父の末っ子として生まれた私は、我が家の栄華も、美観を誇った家敷の記憶もなく、物心ついた時には田も畑も家敷も荒れ放題でした。それでも私は、太い梁や高い天井、白い壁のこの家が好きでした。
祖父がプライドをかけて造り上げてくれ、私や子供達をのびやかに育ててくれたこの家に、新しい生命を吹き込んで見たいと思いました。その思いが「グリ-ン・ツ-リズム」に継がったのです。私が楽しんでいる農の暮らしを、みんなと分かちあいたい!そんな思いを膨らませていったら”ああもしたい””こうもしたい”と夢はどんどん大きくなってゆきます。
けれど現実は厳しいものでした。全国の中でも山形県は「グリ-ン・ツ-リズム」には厳しい県なのだそうです。許可の基準がかなり高く、ここまで努力してやる人が何人いるのかしらと思う程でした。勉強会の時の話とはあまりにギャップがあるので、県の農政課に苦情を言いに行ったこともありました。
それだけでなく、一番身近の母と夫が反対するのでした。頼りにする人に反対されるのは本当に心細いものでした。でも私はやると決めたのです。子供達を説得し、夫に理解を求めるべく再度話合いです。ドラマティックな話し合いの末、夫も納得してくれました。 母は最後まで反対でしたが、手配しておいた宮大工さんをこれ以上待たせるわけにもいかず、夫と共に資金繰りです。雪が舞う季節になりやっと3ケ月遅れで着工出来る事になりました。「グリ-ン・ツ-リズム」をスタ-トさせるには、まだまだ解決しなければならない問題が山ずみです。
98年は、下地づくりに奔走してきましたが
99年は、祖父から受け継いだものを活かし、私らしい農の華を開かせてみたいと思います。
庄内協同ファ-ムだより 1998.11月発行 No.48
収穫の秋は大さわぎ
妻の身体の異常に気付いたのは、夏の暑さも遠退いた8月下旬の頃でした。稲刈りの後に出荷を計画していたストック(ナタネ科の切り花)の八重鑑別作業を、数日暑いハウスの中で続けたせいか、夜になると足がだるくむくみも確認できた。指で少し押すと指の跡が残り「おかしいなあ」と妻が言う。
翌日、病院で診察を受けたら蛋白と糖が出ているとのことで一日の検査入院をすることになった。本人は身体に特別の異常を感じていないし、農作業と夏の疲れがでたのかなあとその時は軽く受け止めただけでした。
何度か病院に足を運んでも検査結果がわからないと言われ、漸くして病名がはっきりしたのが9月の中旬にもなってからでした。担当の医師から「腎臓の病気で治療しないと人工透析になります。」と言われたとのこと。すぐ入院するように言われたという。
農家にとって9月という季節はめちゃくちゃ忙しい。稲刈りを前にしてコンバイン、乾燥機、米の出荷までの機械器具の点検と組立て作業やら、稲刈り前に収穫しなければならないハトムギの刈り取り。ストックの灌水と管理作業がぎっしりと詰まっている季節なのです。今ここで妻に農作業から離脱されたらと考えると身体が沈みこむような重圧を受けた。
2年前にも田植え直前に胆石の手術で20日余り入院し、その時の大変だった事が蘇ってくる。
農家の労働は夫婦単位の協働を基本としてなりたっていると思っているのだけれど、こうした非常事態になると農家という労働形態の脆さがあらわれてパニックになってしまう。
妻の労働のピンチヒッタ-は70才を越えた父と母になるのだけれど、母は今年の春に軽い脳こうそくを患って無理ができないし、父とて近年は農作業からリタイヤしていたから、二人で妻一人分ということもできそうにない。結局、親戚のおかあさん二人の応援をもらって長雨で圃場条件の悪い中での稲刈りを10月中旬に終了することができました。
妻の入院で大変な思いもしたけれど、とても貴重な体験もしたなあと思います。ここ数年住宅の新築やら子供たちの進学、ぐらついた農業経営を立て直すために二人で必死に走り続けてきたのかもしれません。走る速度をゆるめて道端に咲いているタンポポや野菊の花に気付く余裕を持ちなさいという啓示だったのだと気づかされました。
スケッチ
11月16日、中旬だというのに降霜もなく暖かい晩秋をぬくぬくと楽しんでいた。このまま雪のない暖冬かなと予想していた矢先、天気予報はあさってから真冬並の寒気団が入り強い冬型になるとの事、慌てて畑に向かい当分食べるだけの野菜をとりこみ冬支度に取りかかった。
しだいに強風が吹き荒れシベリアから越冬の為に飛来してきている白鳥が最上川河口に帰る夕方頃、台風並の強い風に遭い墜落し20羽ほどが負傷し6羽が死んでしまった。18日、初雪が降りその後も降り続け大雪となった。
19日の朝、4時頃修学旅行で大阪に行く高校2年生の息子を駅まで送る為、外に出ると柿の木が倒れビニ-ルハウスの1棟が倒壊してしまっていた。
水分を含んだ湿った重い雪が降りつもった為で、予想をはるかにこえて積雪量は35㎝程、除雪車が出動して来た。
11月に除雪車が走るのを見るのは初めてのこと、雪には慣れている私達も唖然としてしまった。果樹農家のぶどう棚の倒壊や、きのこ栽培用のビニ-ルハウスの倒壊が相次ぎ交通も一日中マヒした。
息子の乗るはずだった電車も線路への倒木のため運休、何とかバスなどを乗り継ぎ大阪の宿泊先に着いたのは夜の10時を過ぎていたとのこと、日本海側は大変な一日だった。
今年の庄内平野は台風の被害も他の地域に比べればたいした事がなくヤレヤレと思っていたのに2日ほどで20度近くの温度差である。めまぐるしい季節の変化に身体がついていくのがやっとで毎日の雪かきをぼやきながら、23日勤労感謝の日、農家では「田の神上げ」の日を迎えた。
おもちをついて供え今年一年の作物の収穫に感謝し来春の「田の神下ろし」まで田んぼの神様に休んで頂く。農家にとっての新年は、稲の種を蒔く4月になる。新学期が4月からなのは稲作文化からで、欧米は、麦を播く9月が新学期なのだという説を何かの本で読んだことがある。
畑を耕す春、夏、秋、雪国の冬は生活を営んでいくのは大変だが心楽しい季節である。種を蒔く春が巡ってくるまで、心を耕やし暮らしを耕やすひとときの休息期でもある。
雪がとけたら、畑の片づけビニ-ルハウスの修理、雪囲いなどをして冬への備えを万全にしよう。来年は夫と私のえとのうさぎ年、おだやかな年でありますように。
庄内協同ファ-ムだより 1998.10月発行 No.47
枝豆の出荷を振り返って
今年の夏は雨が多く、枝豆の収穫にはとても苦労させられました。
雨合羽を着て、田植え長靴を履いての作業は身体にはきつく、一体いつまでこの雨は続くのだろうかと思うほどでした。
畑から持ってきた枝豆を機械で莢(さや)だけ取り外しますが、雨にぬれた莢は泥だらけのために水洗いをし脱水機にかけます。 雨のおかげで仕事は倍にも増えてしまいます。枝豆の収穫作業は思っているよりずっときついものなのです。
それだけに、だだちゃ豆を買って食べてくれたお客さんの”おいしかった”の一言は”俺の人生はだだちゃ豆”と天にも昇る気持ちになるものです。反対に”たいしたことないわね”と言われたら”どうしてだろう”と自信をなくしてしまいます。
生産者はこのような極端な気持ちの間を揺れ動きます。そして今年こそはという気持ちで立ち向かっているのです。
枝豆を作って20年以上になります。技術的にはそれなりのところまで成果が見えるのですが、それでもまだ課題が残されています。
今年水稲の無農薬栽培をやってみました。報告できるようなものはまだありませんが収量は反当6俵でした。来年もやります。反省する事は山ほどあります。来年の収量は9俵が目標。言うも行うもほんとうに大変な無農薬栽培。
スケッチ へちまのこと
鳥海山の初冠雪、冬の使者白鳥のシベリアからの飛来と恒例のニュ-スが聞かれる季節となりました。
そんな中「庄内協同ファ-ムへちま部」がみなし法人「 」と名称も新たにスタ-トをきりました。内容はすでにご案内の通りですが八彩耕房は全員で検討の結果、菅原すみさんの提案した名称に決定しました。
その思いなど挨拶文から抜粋しますと「八彩耕房」は[へちま部員であった、女性八人が、それぞれの放つ色彩を農村の暮らしにいかし、土を耕しながら生きていきたい]という思いからつけたものです。「へちま部」も、もちろん長い間、親しまれて来て、ストレ-トで分り易く、良かったのですが、一つの生産団体として経営管理をするためのステップアップをはかる意味からも、新しい風を取り入れ更なる向上を目指したいという思いがありました。
さて、前回のファ-ムだよりで餅の製造過程を野口さんが詳しく説明してくれた文章を興味深く読み、私共もファ-ムの組合員の一員でありながら、知らない点は多く、「へぇ-そうなのか」と納得したものです。今回は皆さんにより理解してもらうために、へちまについて記してみようと思います。
へちまの種子は、かぼちゃの種子よりやや小さめで黒色。普通、種苗店から買い求めますが、自家採種も可能。(大きくて立派な実の種子を取る)
苗代の苗と同時進行で育苗し、苗代後のハウスを利用して定植します。(個人差はあるが6月初旬~中旬頃)私は、6月5日に定植。もちろん、無農薬有機栽培。除草の為の黒マルチを張り、その下には灌水チュ-ブを通します。
ある程度、成長するとハウスのビニ-ルを取りはずしネットを張り、側枝の整枝誘引と、この頃がかなり忙しい作業になります。
盛夏には、へちまのハウスがすっぽりと緑に覆われ、直径10㎝程もある鮮やかな、黄色の花が咲き乱れ風にそよぐ様子は、とても美しいものです。その下は、丁度良い日影でぶらぶら揺れるへちまの実を見上げながら、ほっとする時間です。
採水は暑さの柔らぐ9月からになります。我家の場合は、9月11日から3日間で採水を終えました。稲刈りと採水作業が重なると、体力的にきついので稲刈り前短期間で終るようにしています。 酒造会社に依頼した洗浄、封冠済みの一升びんを使用。もちろん、へちまの茎、カッタ-ナイフ、手など消毒し、地上60㎝位で切りびんに差し込み、雑菌が入らぬ様、アルミホイル、脱脂綿等でしっかり封じ、びんは遮光のため新聞紙で覆います。
人間にも個人差がある様にへちまにも茎を切ったとたん、ポタポタと液があふれ出るものがあれば、ゆっくりゆっくり、マイペ-ス型もあり、同じ畑で同じ条件で育てたはずなのに不思議なものです。 採水後の一升びんは直ぐろ渦し20㍑入りのポリタンクに入れ冷蔵庫から冷凍庫保存となり、注文に応じて解凍、びん詰め、低温殺菌処理して製品となります。
へちまたわしは、水につけて皮をむき、何度もきれいに水洗いをして、乾燥して製品になりますが臭くて大変な作業です。もちろん無漂白で安心してご使用いただけます。
「八彩耕房」の挨拶文の中にもありましたが、種蒔きから製造まで、自分達の手で創り上げた製品なので愛着も大きいです。若干クレ-ムの問題点も有りますが、皆で知恵を出し合い、分析デ-タ-に基づき解決の方向に進んで行きたいと思っています。
昨年、へちま水のパンフレットを作成し女性八人が手分けして売り込みに動きました。その消費者との交流会で「へちま部の皆さんは、へちま水を使っているからお若いのですね」とよく話になりました。
もちろんお世辞です。90%お世辞でしょうが、残り10%には、私達の自ら創り上げたへちま製品に持っている自信や誇りが顔や表情に現れているのだと自負しています。
こんな私達。5年後、10年後、孫をうば車に乗せ傍らに遊ばせてへちま畑でせっせと汗を流していることでしょう。
庄内協同ファ-ムだより 1998.9月発行 No.46
「餅の製造が始まります。」
1年のたつのは早いもので、春にまいた稲が黄金色になって首を垂れていますが、収穫間近の9月16日の台風は私の田圃の稲に被害をもたらしました。ひとめぼれの穂は地面につくほどに低くなり、もちの稲は若干倒れてしまった。もちの茎は太いし丈夫だが、うるち米より少し丈が高いためか、この間のような強い風雨には耐えられず根元からポッキリと折れてしまった。刈り取り作業が大変だなと、今から頭をかかえているところですが、そんな中で、刈り取りでのもち製造を終えた新米作業が10月よりスタ-トします。本格的には、刈り取りが終了する中旬以降になりますが、新米で作った餅は最高です。どうぞよろしくお願いします。私は毎年、収穫後に餅の製造仕事を加工場に来てやっています。そこで、まだ作り方を良く知らない方に、私たちの標準的な製造作業をご紹介します。
(1)玄米を精米機で精米します。(この時に石抜きや、着色米を省きます。)
(2)洗米機で1回30㎏の米を洗い、きれいな水に一晩浸漬して、翌日に蒸米機で蒸すのですが、今年は蒸米機を増やし玄米用と白米用の2台で作業をすすめる予定です。蒸された餅米が出てきた時は、ピカピカに光って大変きれいです。それを時々食べてみるのですが、これは、本当に美味しいと思います。
(3)次に餅つき機で2~3分の間でついていくのですが、コシがありすぎて餅も杵と一緒に上がってしまう時もあります。粘りと甘みとなめらかな舌触りの餅がこの作業で出来上がります。
(4)つき上がった餅は丸もちと切りもちなどになりますが、形を作るために切り餅はポリシ-トを敷いた型枠に入れ、丸餅は丸い形状で出てくる丸餅カ ッタ-機を使います。出来上がった餅は常に温度を冷ますため、ポリシ-トで覆い棚に入れ風をあててます。1回についた餅がだいたい4枚くらいの枠箱に並べられますが、1台120枚の棚に入ったものを棚台ごと冷蔵庫に入れて餅の放冷します。約2日後に硬くなり袋詰めが出来るようになります。
(5)計量をしながら袋に詰め、金属探知機でチェックします。その後に脱酸素剤を入れながら袋とじ(シ-ラ-)をして、ダンボ-ルの箱に入れて完了です。ちなみに包装材の袋は4年前から塩素ガスの発生しないガスバリァ-の袋を使用してます。
こうして、皆様にお届けしていますが、12月の需要期には出荷前に再チェックをしてより品質の確実なものをお送りするようにしています。
今年も美味しくて、安全な、お餅を皆様にお届け出来るよう頑張りたいと思います。
スケッチ
枝豆の収穫もやっと終わり、ホットする間もなく稲刈りの準備に入る。体が疲れているとなかなか仕事がはかどらない。そんな時は、あせらずのんびりと、ストレス解消といこう!
野良着のまま、ちょっとドライブへ、車で10分位走ると、雄大な日本海がみえてくる。ウインドサ-フィンやサ-フィンに興じる若者たち。岩場ではのんびり磯釣りを楽しむ人たち。そんな風景を車中から眺めながら、北に向かって走ると山すそを海に浮かべてそびえ立つ鳥海山(出羽富士)の雄姿が目に入ってくる本当にすばらしい景色ですよ。
ちょっと小耳にはさんだのですが、この庄内浜が、ハマちゃん、ス-さんでおなじみの釣りバカ日記のロケ地になるらしいですよ。 お正月が楽しみですね。
一息ついて元気が出たところで、今年の枝豆栽培を振り返ってみようと思う。
今年は大変な異常気象で、春の育苗の時期に真夏のような高温が続き、丈夫な苗を育てようと張り切っていたのに!
この時ばかり太陽が恨めしく温度を下げるのに(育苗ハウス内の)必死。しかし、所詮は天気に勝てず。納得のいく苗を育てることができなかった。また、枝豆は機械植え一年生で、思い通りに定植できず四苦八苦しながら植え付けた。
その機械植えの1本植え(手植えは2本植え)が災い転じて福となし、梅雨の明けない夏をのり越えて、なんと!
1本で450g(普通180g)にもなる枝豆に成長したものあり、思わず、おとうさんと顔を見合わせニッコリ。枝にビッシリ豆をつけていました。春の疲れが一気に吹き飛んだ瞬間でした。
おいしいと喜んで食べて下さるお客様がいらっしゃるかぎり、無農薬、無化学肥料でがんばっていきたいと思っていますので、今後共宜しくお願いします。
庄内協同ファ-ムだより 1998.8月発行 No.45
「冷夏・・・米の行方は?」
今年は梅雨の明けないままに秋を迎えるという。14日に気象庁の「東北、北陸の梅雨明け宣言はしない。」という発表は5年ぶり、あの大冷害の年以来の事。7月末の稲の作況指数も全国97のやや不良との発表であった。
ここ庄内は7月末までは好天が続き、太平洋側の人たちには悪いが、稲も順調に生育し、出穂も5日程度早くなると見込まれて豊作型の出来だった。しかし8月に入った途端、雨続きの肌寒い日が続き、イモチ病の発生が心配されはじめた。
異常気象といわれて久しいが、台風の数も極端に少なく、つい5年前の大冷害が頭をかすめる。昨年までの米余りの対策で減反が大幅に強化された中では、平年作でも新米だけでは来年の需要に間に合わないのが春からわかっていたのだが。 そういえば ゛柔ちゃん゛が宣伝していた「たくわえくん」とかの古米販売コマ-シャルがこの頃、なくなってしまった。自由に作り、自由に売れるはずだった「食糧法」の下で、減反はさらに強化され、米価はどんどん下がった。作る自由は、政府に変わり農協がさらにしめつけ、売る自由は市場価格の名目で操作され続けられているように見える。思い過ごしなら良いのだが、米不足になったら、どんな反動があるのだろう。5年前のように外国産米は買いあされない・・・。 ところで、8月は鎮魂と民族移動の季節。私のムラでも13日のお盆には大勢が帰省し、14日の秋祭りの夜は、久しぶりの顔がそろいにぎわった。ビ-ルを片手の話だが、都会もあんまり景気よい話はないという。マスコミ報道以上に不況という。農家の長男はいいなどというヤツまでいる。「故郷に錦を飾る」たとえのように、こんな話はしたことがなかったのに。
翌15日は53回目の敗戦記念日。
そして、私の49回目の誕生日・・?! 庄内協同ファ-ムの産直提携米をよろしくお願いします
農業日誌
♪おいし水♪
一杯の水で記憶を呼びさます事があります。
残暑の中、砂丘のメロン畑の後片づけ。ふっと思い出した曲が「おいしい水」!ボサノバ調だった様な?変わった曲名、リズミカルな曲調、何故か思い出した。 忙しい、気ぜわしいメロンの収穫が終わり、ほんの少し気持ちに余裕が出来てきた自分に気がつく時です。
夏ばて気味の体は思う様に動かず、汗まみれ、砂まみれ。そんな畑で、木陰の一杯の冷たい水は、うまさが違います。 車で10分程の我が家の畑。子供の頃は、牛車で1時間程かかり、昼食持参、家族総出の一日作業でした。
夏の暑い時期は、日影に置いた水さえ、熱く感じる程で、昼までにはそれも飲みきってしまうものでした。今では、それぞれの畑にはポンプで汲み上げる井戸があり、エンジンをまわせば注水し、乾いた喉もうるおしてくれます。
あの頃は、そんな時いつも母が「ハチノスさいって、はっこい(冷たい)水くんでこいや。」そう言って、弟と二人に小さな水入れ用のタルを持たせられるものでした。
500m程離れたその場所は、以前に大きなハチの巣があり黒松林に囲まれ、ひんやりとした木陰のくぼ地で砂の中から出る湧き水、子供心に、川もない砂丘のどまん中で水がわきでる不思議な場所でした。そんな興味の中で、汗をぬぐい、口に含む水のうまさは忘れられません。
水のおいしさ2つめ
「庄内の米は、庄内の水で炊くのが、やっぱり一番おいしいのかなあ。本当に違うんだな、これが!」
先日、久しぶりに我が家に訪れた妻の弟が、ご飯のおいしさを話してくれた。男の子二人を遊佐の西浜キャンプ場に連れて来たついでに、ポリタンクに鳥海山の湧き水をくんで来たという。「1回炊くのに6位水を使うんだけれど、子供らのご飯の量が違うんだ。」
昨年の春まで鶴岡の勤務で、冬の地吹雪には、まいったらしいが魚やお米や水は、気に入ったらしい。
「山辺(妻の実家)で炊いたご飯と、鶴岡でのご飯では、同じ米でも、どうも違うんだよな。これは、水の違いなんだきっと!」
「それでも、そばは、ホントにうまいんでないか。あの味は、鶴岡でゆでても、あのうまさは出ないんだよ。」
「ん・・!お米にあった水と、そばにあった水があるのかもな。」水のおいしさ、水のうまさ、庄内と内陸は違うらしい。
庄内協同ファ-ムだより 1998年7月発行 NO.44
「食わずしては生きられない」
生きると言うことは食うことだ。食わずには何も始まらない。その”食う”為の作ることを農民は放棄し始めた。長年のストレスがここに来て出始めている。転作の強化や米の暴落をはじめとする様々な制度の歪みが一気に噴出し、ガンバレ、ガンバレと言われても頑張りようがなくなって来ている。
農産物を生産するという事は命を育むことだ。その命が軽んじられている。今こそ”食べる”事の意義をもう一度みんなで考えて見る必要があるのではないか。人間は食わずしては生きられないのだから。
今のままだと現場は、村はあと10年、いや5年持つかどうか?決してオ-バ-な事を言っているのではない。日本の中堅農家の平均年齢は既に65才を越えている。米作り農家も今やボランティアにされてしまった。当然、後継者なんて育つはずもない。
ところが、ところがである。ここに”異大”なる農民集団がある。決して”偉大”ではない。その名を庄内協同ファ-ムと言う。みんなが振り向かなくなっている米作りに、農業に必死で取り組んでいる。まさに田舎の天然記念物である。除草剤1回だけ使用して米作りをしてみようとか、全然使わないでカモや鯉や微生物に働かせて高みの見物でいこうとか?しかし、どっこい愚か者の考えることはそんなにうまく行くはずもなく最後に登場するのは昔懐かしい”除草機”と言う事になる。村の連中もその光景を珍しがって寄って来る者や、危険を察知して遠巻に眺めている者など様々だ。
春はドロオイ虫で真っ白になったり、夏は夏でヒエという雑草が一面に茂り、その”異大”さを存分に発揮することになる。懲りない面々はそれでもやけに明るく、いや開き直ってか、ますます熱が入ってくる。
思いと現実のギャップに、もがき苦しみながらも、それでも必死に農業に頑張っている。そんな仲間を私はいつも自慢に思うし誇りに思っている。みんながいるから頑張れる。少々おつむの辺りが寂しくなっても、おなかが出っ張っても、細かい字が見えにくくなっても気にしない。食べてくれる人がいる限り百姓で、頑張って行こう。
それにしても夏は暑い。ビ-ルだ、ビ-ルだ。ビ-ルには枝豆だ!そうです。
協同ファ-ムの枝豆部会は、これからが一番忙しい季節に入ります。
何! だだちゃ豆をしらないだと!
食ったことがないだと!
まずは電話かファックスで、すぐにお問い合わせを。あなたの御一報が村を救うかも知れませんヨ?
田舎のおっさん達は暑く燃えている。
(熱の入る冨樫です。)
スケッチ
羽黒山の花祭り
7月15日に、全国的に知られている出羽三山の一つ霊峰羽黒山で「出羽三山神社の花祭り」がありました。
私の住む鶴岡市平京田は、江戸時代以前(どのくらい昔かは集落の最長老もわからない)に出羽三山神社が火事になり、その煙が集落の薬師神社のほこらから出てきたという言い伝えから、かなり昔から氏子になっていて神殿に奉られてある三基のみこしの一基の担ぎ手として毎年参加します。
義父の若い頃は、前日の午後11時の鐘の音と共に集会所に集まり、みんなで歩いていったということでした。何の娯楽もなかったその当時は、神事であり楽しみの一つでもあったようです。 この日は、庄内一円をはじめ県内外から訪れた祭り客が「稲の花」を奪い合います。
稲の豊作を願う花祭りは、松例祭、八朔祭りとともに出羽三山神社の三大祭りの一つで、稲の花をあしらった依代(よりしろ)の「花梵天」の先に飾られた造花の「稲の花」を家に飾ると豊作になると言われています。
夏の日差しが照りつける中、午後1時すぎ、黄、赤、白の三本の花梵天が月山、羽黒山、湯殿山の三基のみこしとともに合祭殿前の鏡池周辺を練り始めると、祭りは最高潮。
境内を取り囲んだ祭り客は、高さ約5㍍の花梵天が傾くたびに、われ先にと花を奪い合い池の周りを半周しないうちに三本ともほとんど丸裸にされていました。この祭りが終わるとここ庄内地方にも本格的な夏の到来です。今年の稲の豊作を願って羽黒山を後にしました。
庄内協同ファ-ムだより 1998年6月発行 No.43
スケッチ
『暑い夏が終わりかけた頃、ドイツのコブレンツからキクちゃんがやってきた。「英語だってやばいのにドイツ語だぜ、どうしよう」我が家は大騒ぎ。11月の中旬、妻が協同ファ-ムの仲間たちとイタリアとドイツへ10日間の旅行へ。ストックの花の収穫の真っ最中で私は収穫と出荷で忙殺される。ドイツからFAXで「愉しい旅行をしています。ストックの収穫よろしくネ」としおらしい便り。そして高1の娘が、来年アメリカに留学することが決まり、我が家も世間並みに国際化に飲み込まれました。世の中、自由化とビックバンの時代とかで、もうメッチャクチャ。「我が家」と「ニッポン」どういう新年になりますか』
これは夫が書いた今年の年賀状の文面。
下の娘が高校の国際科に入学。あなたは何ヶ月くらいなら留学生を受け入れますかという入学式の日のアンケ-トで、少しは覚悟していたのですが、思いもよらない展開となりました。昨年の7月頃、娘の家族一人一人への説得に、夫や舅はほどなく承諾。けれども4~5年前から三食すべての食事の担当をしている姑はなかなかすぐに返事を出してはくれませんでした。それでも娘の強い説得で、キクちゃんは我が家へ来る事になり、心配していた言葉は、日本語、フランス語、英語、ドイツ語を流暢にはなせる彼女によってすぐに解決されました。
25年前にドイツに渡ったという彼女の両親ですが、キクちゃんは生まれも育ちもドイツ。なかなか日本人と同じという訳にはいかず、簡単に受け入れを承諾した男達は細かい事でぶつぶつ。そのたびに姑の「家の生まれの者には、よそから来た人の気持ちなんかわからねもんだ。引き受けた以上は気持ちよく帰してやるもんだ。」の一言に、次の言葉を失ってしまいます。
そういえば、私はこの家に嫁いで20年以上たつけれど、姑と喧嘩した記憶が1回あるだけです。姑はあまり口数の多い人ではない分だけ、なれない時は何を考えているのかわからないもどかしさや、やさしい言葉をかけてほしいという思いにかられたものでしたが、慣れてくると、それが彼女流と理解できる様になり、不思議と腹の立つ事がなくなりました。いつも強気で、少々の事では医者にもかからない人でしたが、70をすぎて歳にはかてず、田植えを今年も手伝ってくれてしばらくしてから、左手に違和感を感じた時、異常に高い血圧に一番驚いたのは彼女だったと思います。近くのかかりつけの医院でという姑に病院での検査を強くすすめ、10日余りの入院生活を送る事になりました。
2月からよその家にいっていたキクちゃんも二度も見舞いに来てくれて、彼女が柔道の練習の時に手首を鍛えるために使う器具をプレゼントしてくれ、その後何度か我が家に泊まって、家族全員で見送る中、先日ドイツへと帰っていきました。
我が家は夫と父と母、それに祖父母がおりますから、女性が3人になりますが、ほとんど言い争った事がありません。3人だから逆にバランスが保てているのかもしれませんが、祖母はいつもひかえめで、私の子供達が小さい時に面倒をみてもらいましたが、そのおかげでやさしい子供達に育ってくれたのかもしれないと思ってます。
大家族の中での女性の果たす役割、特に農家にとってはすごく大きいものがあります。今回姑が10日間の入院の時には、私にとっては農作業と家事に追われ、まったく余裕のない日々が続きました。私も2年ほど前、2ケ月間ほど入院しましたが、姑は大変だったろうと想像できます。最近、弱音を吐く姑に、「おばあちゃんらしくないネ」と言うと「一応中風だからネ」と笑って答えました。まだまだ前の様に元どうりになるまではしばらくかかりそうだけれど、一日も早く元気になってほしいと願ってます。
”東京から”No2「立っているところ」
―あの頃―
庄内行き全日空の金をかけた機内誌に、パリの5月革命の話が載っていた。1968年の事だからもう30年も前の話だ。当時の運動家たちも、社会の中枢にまでのぼりつめていて、インタビューした所、あまりに保守的になっていて驚いたとお決まりのオチが付いていた。日本でも当時「意義申し立ての運動」が全国を席巻していて、まだ小さかった私の記憶は断片的なニュースの映像。ハッキリと印象に残っているのは、浅間山荘事件(1972)で、ランドセルを置いてずっとTVを見ていた。
―若い頃―
庄内協同ファームの男衆は、第二次世界大戦に日本が負けてから6年の間に生まれた者が多い。だから同時代に色々なことを見て感じていたと思う。同じ農民の問題ということで、だいぶ三里塚(成田)空港の反対運動には心情的な肩入れをしたようだ。小川プロの「三里塚」シリーズの映画上映会を地元庄内でやったのが組織発足(庄内協同ファームの前身の庄内農民レポート)のきっかけだったと聞いている。
農家の長男が当たり前のように跡取りになった最後の世代だ。以前、ある男衆が描いた絵を納屋から引っぱり出して見せてもらったこがある。赤い大きなトラクターの前で誇らし気に腕を組んだ二十歳の彼がいた。彼らが就農した頃はまだ手作業中心の農業で、こんなことを一生やるのかと思うと気が滅入ったという話も聞いた。まだ減反も始まってなく、国民の食糧としての米を増産しようというかけ声が高らかに響いていた。
当時、多くの男衆が通った庄内農業高校には教員に評論家の佐高信(さたかまこと)がいた。「社研」の顧問もやっていて、何人かは部員だった。音楽・美術・芝居が好きで、「少々訳ありの喫茶店」に溜まっていた。今でも、ラッパを吹きバンドをやっている者、絵を描いている者が何人もいる。さすがに芝居はやらなくなったようだが以前は劇団までやっていた。まあ、ちょっとハズレタ、イケテル連中だったのは事実だ。同年代の人なら腑に落ちる、社会という大きな醸造装置が産み出した、とある組織が庄内協同ファームの原形だ。
―それから―
組織を作り、農業問題を語り合い、地元の古老の聞き語りを冊子にまとめ、減反を拒否しようと挑み二軒以外は心ならずも挫折して、農協が買ってくれない仲間の米を売ろうと産直を始め消費者(団体)と出会い(この辺りから私も登場)、稲作中心の農業の冬仕事として餅加工を始め、組織を法人化し、加工場も建て、非農家出身の専従職員も雇用した(みんなの母校庄内農業高校卒業の二十歳のカッコイイ青年もいる)。加工技術は向上し、おかげさまで売上げも伸び、各人の経営に占める産直の割合も大きくなった。
こんな風に書いてしまえば、25年などあっという間だ。ふと集落を見渡せば専業農家の数はどんどん減っている。山場の方では耕作放棄地も増えている。まずは自分たちのことで精一杯だが、自分たちだけでは農業は続けられない。何とか周りの農家のことも考えなければと思うのだが、有機農産物市場はそれ程大きくなく、競争も厳しい。それよりも、大学に通い始めたわが家の子どもたちの将来に頭を痛めている。冴えた青年たちもフツーのお父さんになった(まだカワリモノと言う人たちもいるけれど)。
若い頃からいろんなことをやっている割にはけっこう慎重で、石橋を叩いて壊す(?)と言われた我が男衆は、さらに寄る年波を味方に付けて例に漏れず保守化してきた。パリも庄内も変わらないだろうし、新しいことに挑戦する気力はともすれば失われがちだ。どんなに過去が素晴らしくても昔は昔で、大切なのは今やっていることだ。今年などは水田の除草のため、ある農法(やり方)に多くの人が取り組んだ。「鴨」や「鯉」も使っている。農薬や化学肥料の使用量を減らす為の実践も年に一度しか試せない。失敗したら経営上大打撃になる。これといって確立された農法が無い中で地道な努力が続いている。
―これから―
「環境ホルモン」や「遺伝子組み換え農産物」に大きな関心が集まる中、組織で直接加工しているものについては包装資材もすでに対応が済んでいる。各人が生産加工しているものについては遅まきながら点検を始めた所だ。使用済み農業資材の処分方法や、組織では出荷していないが畜産の飼料(ほとんどを輸入に頼っている)等すぐには解決できない問題もある。切ない話だがそれを言い訳にせずやっていけたらと思っている。
「環境ホルモン」や「遺伝子組み換え農産物」の問題は、マチに住もうがムラに住もうが等しく、「さてどうするんだい」という問いかけを私たちに発している。現在の暮らし方が問われているのだ。問題提起や警鐘を鳴らす時は過ぎ、後はできることできないことを正直に語りながらの実践しかないだろう。私たちの歩みは遅いかもしれない。けれど、今起きている問題を全身で受けとめて、美味しくて安全な農産物や加工品をこれからも作り、届けていく。
夏の企画品どうぞよろしく。
庄内協同ファ-ムだより 1998年5月発行 No.42
苗箱にミミズの赤ちゃん
我が家は今年もマイペ-ス(?)の農作業をしている。気温が高い日(30度をこえる夏日もあった)が多く、苗の生育が予想以上に早かった。苗にせかせられる様に農作業が進み、5月初めに田植えをした農家もあれば、私のように5月19日の田植えといった調子もある。
周囲の農家より7~10日遅い種まきを4月19日にした。箱詰めした土に白いカビがたくさん見える。手伝いの子供たちから「お父さん、こんなカビだらけの箱に種まきして大丈夫だ?育たないのでは?」との声。悪いカビでなく、有用な放線菌だから心配ないと思うのだが....。不安な気持ちを抱きながら、生育を見守った。
好天に恵まれ肥料を少し控えすぎたため、葉の色は淡いが、しっかり根張りも良くみるからに丈夫そうな苗ができた。育苗中の防除も薬剤でなく、玄米酢、木酢、天恵緑汁等を2回ほどやっただけだ。本田の肥料も有機100%の取り組みをした。 周囲の田植えがすっかり終わった5月17日に代掻きをし、19日に田植えをした。田植えの際、苗の根の部分が赤いのに気がついた。 カビ?よく見ると糸状のものが動いている。なんとミミズの赤ちゃんのかたまりだった。他の苗も見ると赤い糸のかたまりがあった。有機100%のためなのかは定かでないが、小さいミミズの赤ちゃんを見て、何故かうれしい気持ちになった。
水の中にも小さい生き物たちがたくさん動きまわっている。生き物に囲まれたなかでの農業だ。
毎年、より安全な農作物作りへの取り組みは、失敗をくり返しながらも、少しずつ確かなものがみえてきた様な気がする。
私が田植えを遅くするのには理由がある。畑作業(だだちゃ豆の種、枝付け)との関係もそうだが、カモによる除草で無農薬栽培の稲作りをしているからだ。 カモのヒナ(生後1週間)を田に放つ日(今年は27日の予定)から逆算して田植えの日を決め、代掻き日、種まきの日を決めている。田植え後、日数があきすぎて、ヒエが大きくなるとカモがヒエをよけて除草をしないのだ。気温が高くならないと、カモが寒さで死んだり動きが悪かったりするので、5月下旬にならないとカモを本田にいれられないのだ。今年は90a分を無農薬有機栽培で取り組む計画でスタ-トした。ほかは除草剤1回使用、有機率70%(N換算)の低農薬栽培だ。 種モミの消毒は、60度のお湯に15分間つける方法で済ませた。種まきする土も化学肥料は使えないので、有機100%のぼかし肥料をまぜてやった。当然土壌消毒剤や、育苗のための薬剤も使わなかった。
”東京から”NO.1 「5月」
月に一度は、打ち合わせや会議のため庄内に行く。東京からの交通手段は、上越新幹線新潟経由、羽越線特急乗り換え鶴岡まで約4時間かかる。羽田から一日3便の飛行機だと庄内空港まで約1時間。空港から事務所までは、誰かに迎えに来てもらうこともあるけれど、ここの所のお気に入りはバスと徒歩。最寄りのバス停で降りて20分位、国道をはずれ集落を抜け田んぼの中の農道をぼっちらぼっちら歩く。今回は天気も良くおまけに爽やかな風まで吹いてくれて、例年になく早く田植えが終わった田んぼの中を歩いて行く。驚いたムクドリが慌てて飛んでいった。カエルの大合唱はもう少し先だ。 ここら辺りの水田の一枚の大きさは3反(900坪。約30アール。1アールは10m×10m。)だから、端から端までけっこうな距離がある。
機械の能力かその水田のくせか個人の性格か。きれいに並んで植えられた苗も良く見ると、微妙に曲がっていてオモシロイ。きっと何か考え事をしていたんじゃない、ほらあんなに曲がっている。君のせいじゃないよね。秋には大きな実りを頼むよ。
さて主たる用件の会議の方は、缶入りのお茶のコマーシャルじゃないけれど、「日本の会議は」というやつで終わったのが夜の11時半過ぎ(どこも同じかな)。その後、ぐちゃぐちゃしみじみハハハと酒飲み話しで、午前の3時半。もういい加減と、ひとり事務所で眠ろうと灯を消すと窓がほの明るい。月かと思い窓を開けるともう空が白みはじめている。東京よりずっと夜明けが早いんだ。
春はみんな忙しく誰も遊んでくれない。こんな感じも悪くないなと帰り途、羽田の滑走路の際にはシロツメグサ。