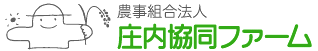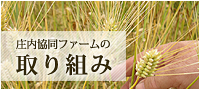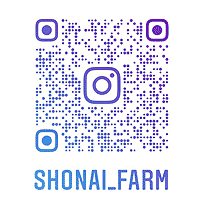楽しきかな自然農業③
≪今年も進む柿の剪定作業≫
2025年2月 志藤 正一
2025年も1ケ月が過ぎ、正月気分からいよいよ今年の作付け計画や作業に取り掛かる時期だ。我が家では積雪の状態を見ながらの柿の剪定が一年の作業の始まりになる。
家から2キロほど離れた里山にある柿園は作業道が積雪に覆われ通ることができない。
冬季にも除雪される市道から先約1キロの坂道は歩いていくことになるが体力が年々低下する我が身にとってはなかなか辛い。そこで最近はスノーモービルの力を借りることにしている。新雪に着いたウサギやキツネの足跡を見ながら山道を登っていくのも獣たちが暗躍する光景を想像できてなかなか楽しいものだ。
一昨年に続き昨年も天候の異常は続いて現れた。比較的災害が少ないと言われてきた我が「庄内」も7月の末には過去に例のないような水害が発生した。我が家のすぐそばを流れる京田川が氾濫し、住宅以外の建物3棟が浸水した。この時の大雨を境に天候は一転、8月は真夏日の連続で水害の後片付けも思うにいかなかった。
化石燃料の使い過ぎや環境破壊による温暖化の影響は間違いなく地球全体を覆っているようだし、我々の足元にもそれが形になって現れているようだ。庄内の農業にも深刻な影響を与えて来ている。お米は収量の指数が92(東北では一番低い)、枝豆の収量も50から60%とかなり低い。その中で唯一“柿”は高温の影響が逆に良いほうに出たのか果実が大きく平年と比べて1.25倍もあり糖度もかなり高かった。
私が長年学んでいる自然農業の指導者趙漢珪(チョウハンギュ)先生は『自然は常に変化するものであり平年はない、平年値とは数字上作られたもので参考にすることはできるが、我々農業者は常に変化する自然や作物の状況を五感で受け止め、これに対処する知恵を持たなければいけない』と言われている。
先生の言われることは理解できるのだがこれを農業の技術として形にするのは容易なことではない。しかしできないとは言いたくないので試行錯誤を重ねながらたどり着くのはやはり基本的な考え方である。
柿でいえば有機肥料を施し、土着の微生物を活用した「ぼかし肥」を施しての土つくりから始まる。農薬での防除をなるべく少なくするには日当たり風通しの良くなる様な樹形を作らなければならない。その為には整枝が重要である。また剪定はその年の実の数(着粒数)をほぼ決定するのでこの二つを一緒に考えながら枝を切り進めていくのが整枝・剪定である。
整枝・剪定は一年の始まりの仕事であると同時に柿の栽培にとって一番重要な仕事といえるかもしれない。整枝・剪定はどんな天候の年でも作業のやり方は変わらないが、着果した実を適度に選別して間引きをする摘蕾・摘果作業は天候やその年の生育によって加減を必要とする作業になるかもしれない。大きい果実を収穫するためには欠かせない作業であり、秋の収穫作業に次ぎ労力を多く必要とする作業になる。
柿の栽培で重要な肥培管理は一つには肥料のやり方がある。ほかの作目と同じく元肥は春肥として多くやらずに秋に収穫後半に施す。落葉してから約1か月は柿の根は活動しているといわれるからこの時期に肥料分を吸収してもらう。春肥が余り良くないのは柿の根が活動し始めるのは発芽の1ケ月後5月の上旬になる。この時期(雨の多い年などは特に)窒素成分が多く吸収されると6月の下旬から7月に上旬にかけて落果(生理落果)を誘発する。
この時期は柿がこの年の結実の数と翌年の花芽分化を同時に行う重要な時期であるので、それより1ケ月早く5月下旬から6月初旬にかけて摘蕾作業を実施し、柿に危機感を抱かせることが二つ目、またこの時期に骨粉を主体にしたリン酸ぼかしを施し、リン酸とカルシウムの吸収を促し、窒素過多に陥らないようにすることが三つ目の要素となる。
自然農業ではこの時期を交代期と呼んでいるが、単年作物と違い果樹の場合は当年の結実と翌年の花芽分化が同時に進行するのでより重要な時期となる。またこの時期は梅雨の時期とも重なるのでさらに管理が重要になる。
自然農業を志してもう30年になるが、この頃になってようやくやはりこのやり方は正かったと思えるようになってきた。大雨、酷暑の影響で米・枝豆共にこの地域の収量が激減する中、自然農業はその底力を発揮しているように思う。我が家の収穫は平年の80%から90%を確保しているし、柿は天候の影響もあったと思うが100%を超えている。これまで自然農業をご指導いただいた趙漢珪(チョウハンギュ)先生や共に学んできた仲間に改めて感謝したい。
加齢とともに多くの面積を栽培するのは難しくなってきたが、今年も豊かな実りを期待して、剪定作業に精を出したいと思う。